砂ずり(砂肝)のコリコリした食感が好きだけど、どう下処理すればいいか分からない、臭み取りはどうするの?と悩んでいませんか。
砂ずり(砂肝)は、スーパーで手軽に手に入りますが、砂ずりと砂肝の違いや、そもそも砂ずりがどこの部位なのか知らない方も多いかもしれません。
砂肝を下処理しないとどうなるのか、硬さや臭いが残ってしまう不安もあります。
また、砂肝が臭いと感じたとき、腐ってるのかどうかの見分け方も気になります。
この記事では、砂ずりの下処理を簡単に行う方法、特に砂ずりの下処理や切り方(銀皮の扱い)、そして気になる臭み取りのテクニック(塩、牛乳、酒)を詳しく紹介します。
砂肝を茹でる場合は何分が適切か、下処理後の砂ずりの保存方法まで網羅します。
砂ずりの下処理と臭み取りのコツを掴んで、家庭でおいしい砂ずり料理を楽しみましょう。
- 砂ずり(砂肝)の基本的な知識と下処理の必要性
- 銀皮の簡単な取り方(切り方)と臭み取りの具体的な手順
- 塩・酒・牛乳を使った臭み取り方法の比較
- 下処理後の正しい冷蔵・冷凍保存の方法
砂ずり下処理と臭み取りの基本

- 砂ずり(どこの部位)と砂肝の違い
- 砂肝は下処理しないとどうなる?
- 砂肝が臭いのは腐ってるサインか
- 砂ずりの下処理を簡単にする方法
- 砂ずりの下処理と切り方(銀皮)
砂ずり(どこの部位)と砂肝の違い
砂ずりと砂肝は、呼び方が違うだけで同じ部位です。
主に地域による呼び名の違いが理由となっています。
一般的に、東日本では「砂肝(すなぎも)」、九州や関西などの西日本では「砂ずり(すなずり)」と呼ばれることが多い傾向にあります。
どちらも鶏の「砂嚢(さのう)」という器官を指します。
砂嚢は、人間でいう「胃」の一部にあたります。
鶏には歯がないため、食べた穀物などを細かくすりつぶす役割を持っています
食べ物と一緒に飲み込んだ小石や砂がこの器官に溜まることから、「砂肝」や「砂ずり」と呼ばれるようになりました。
なお、店頭に並ぶ際は、砂や石はきれいに取り除かれています。
食物をすりつぶす強力な運動を担うため、砂嚢は脂肪がほとんどなく、厚い筋肉でできています。
これが、他の部位にはない独特のコリコリとした強い食感を生み出しているのです。
豆知識:「ずり」の由来
「砂ずり」の「ずり」は、鶏が砂嚢(砂ずり)で砂や小石を使って餌を「擦り(すり)」つぶす様子から来ているという説があります。
焼き鳥店などでは、略して「ずり」と呼ばれることもあります。
砂肝は下処理しないとどうなる?

砂肝(砂ずり)は、下処理をしなくても食べることは可能です。
しかし、下処理をしない場合、食感や風味に影響が出ることがあります。
主なデメリットは以下の通りです。
硬い食感になる
砂肝についている青白い皮「銀皮(ぎんぴ)」は、焼くと特に硬くなります。
これを取り除かないと、噛み切りにくい、ゴムのような食感に感じることがあります。
臭みが残る場合がある
砂肝は内臓肉の中では比較的臭みが少ない部位ですが、個体差や鮮度によっては特有の臭みを感じることがあります。
また、銀皮の周辺や筋の間に残った血合いや汚れも、臭みの原因となります。
火の通りや味の染み込みが悪くなる
砂肝は厚みのある筋肉です。
下処理で切り込みを入れたり、適切に切り分けたりしないと、中心まで火が通りにくくなったり、味が染み込みにくくなったりします。
特に注意が必要なケース
砂肝の硬い食感が特に苦手な方や、臭みに敏感な方は、下処理を行うことを強くおすすめします。
逆に、しっかりとした歯ごたえが好みという方は、銀皮をあえて残す場合もありますが、その場合でも臭み取りや切り込みを入れる工夫をすると良いでしょう。
結論として、必須ではありませんが、より美味しく、食べやすく仕上げるためには下処理を行うのがおすすめです。
砂肝が臭いのは腐ってるサインか

砂肝が「臭い」と感じた場合、それが鮮度の問題である可能性と、腐敗している可能性があります。
砂肝特有の臭いと、腐敗による明らかな異常臭は区別する必要があります。
通常の臭み
鮮度が良くても、内臓肉特有のわずかな臭いを感じることはあります。
これは、血合いや表面のぬめりに由来することが多く、後述する「臭み取り」の下処理で軽減できます。
腐敗のサイン
以下のような特徴が見られる場合は、食べるのをやめてください。
- 強い刺激臭(アンモニア臭): ツンと鼻を突くような、明らかな腐敗臭がします。
- 表面のぬめり: 触ったときに、糸を引くような異常なぬめりがある。
- 色の変化: 鮮やかな赤色ではなく、暗褐色やくすんだ色に変色している。白い部分(銀皮など)の透明感がない。
- 弾力がない: 指で押したときに、ハリがなくブヨブヨしている。
鮮度の良い砂肝の選び方
購入時に新鮮なものを選ぶことも重要です。
- 色: 鮮やかな赤色(あずき色)で、ツヤがあるもの。
- 銀皮: 白い部分(銀皮)に透明感や青みがあり、くすんでいないもの。
- 弾力: 身にハリがあり、引き締まっているもの。
パック内にドリップ(血水)が出ているものは鮮度が落ち始めている可能性があるため、避けるのが無難です。
購入後は早めに使い切ることが基本です。
もし腐敗のサインが見られた場合は、加熱しても安全に食べられないため、残念ですが廃棄してください。
砂ずりの下処理を簡単にする方法

面倒な下処理を簡単にする方法として、「銀皮を取らずに丸ごと茹でる」というテクニックがあります。
この方法なら、包丁で銀皮を細かく取り除く手間を省きつつ、臭み取りと食感の改善を同時に行えます。
具体的な手順は以下の通りです。
- 砂ずりをパックから取り出し、軽く水洗いします。
- 鍋にたっぷりのお湯を沸かし、砂ずりをそのまま入れます。
- 火加減はグラグラする程度を保ち、約12分〜13分しっかりと茹でます。
- 茹で上がったら火を止め、水に取ります。
- 水の中で砂ずりの表面をよく洗います。表面についている余分な皮や脂、汚れをこすり落とすイメージです。
- 水を1〜2回替えながらしっかり洗い、臭みの元を取り除きます。
- 洗い終わったら、キッチンペーパーなどで水気をしっかり拭き取ります。
この方法には、以下のようなメリットがあります。
- 手間が少ない: 包丁で銀皮を削ぎ落とす作業が不要です。
- 臭みが取れる: しっかり茹でて洗うことで、臭みの原因となる汚れや脂が落ちます。
- 銀皮も食べやすくなる: 焼くと硬い銀皮も、茹でることで柔らかくなり、コリコリとした食感を残しつつ食べやすくなります。
- 保存性が高まる: 加熱処理することで、下処理後の冷蔵保存期間が少し長くなります(例:冷蔵で2〜3日)。
この方法がおすすめな料理
この下処理方法は、和え物(ごま油和え、ポン酢和えなど)や、一度下処理したものを再度炒め物(ピーマンとのオイスターソース炒めなど)に使う場合に特に便利です。
砂ずりの下処理と切り方(銀皮)

砂ずりの独特な食感を最大限に活かす伝統的な下処理は、「銀皮(ぎんぴ)」と呼ばれる青白い部分を包丁で取り除く方法です。
銀皮は焼くと硬くなるため、これを取り除くことで、砂ずり本体のサクサク・コリコリとした食感を際立たせることができます。
砂ずりは、中央でつながった2つのコブのような形をしています。
銀皮は、この2つのコブの側面(谷間の部分)についている青白く硬い皮(膜)のことです。(※コブの裏側についている「白い皮(膜)」は銀皮とは別物ですが、これも取り除くとより食感が均一になります)
銀皮の取り方(包丁を使う方法)
- まず、砂ずりを2つのコブに切り分けます。
中央のつながっている部分に包丁を入れ、半分にします。 - 銀皮をまな板に押し付けるように砂ずりを持ちます。(皮(膜)がついている面を上にする)
- 包丁を銀皮と身の間に寝かせるように入れます。
- 包丁をまな板に沿わせるように、銀皮に刃をピタリと当てたまま、身を削ぎ取るイメージで切り進めます。
- (ポイント)魚の皮を引く感覚に近いです。包丁を銀皮から浮かせてしまうと、銀皮側に美味しい身が多く残ってしまうので注意が必要です。
- 反対側も同様にして、銀皮を取り除きます。
銀皮以外の処理(任意)
銀皮を取り除いた後、コブの裏側に残っている「白い皮(膜)」が気になる場合は、同様に包丁を寝かせて削ぎ落とします。
これを取ることで、さらに均一な食感になります。
下処理後の切り方
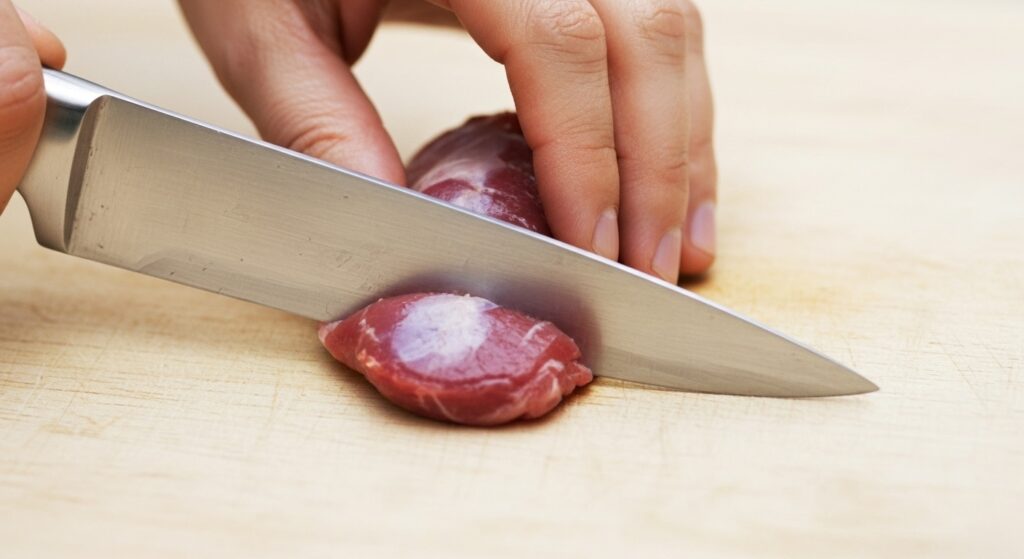
火の通りと味染みを良くする「切り込み」:
- 川の字: 銀皮を取り除いた(または残した)砂ずりの厚みのある部分に、縦に2〜3本、浅く切り込みを入れます。
- 格子状: 川の字に切り込みを入れた後、向きを変えてさらに斜め(または直角)に切り込みを入れ、格子模様にします。
見た目が華やかになり、タレも絡みやすくなります。
食べやすいカット:
- 砂ずりが大きい場合は、さらに半分や3等分(薄切り)にカットします。
ライターからの一言
銀皮を包丁で取り除く作業は、慣れるまでは少し難しく、身がもったいないと感じるかもしれません。
ただ、このひと手間で焼き鳥屋さんで食べるような、格別な食感に仕上がります。
炒め物や焼き物で食感を最優先したい場合に、ぜひ挑戦してみてください。
砂ずりの下処理と臭み取りの具体的手順

- 塩を使った基本的な臭み取り
- 酒を使った臭み取りの方法
- 牛乳に浸ける臭み取りの効果
- 砂肝を茹でる時間は何分が目安?
- 下処理後の砂ずりの保存方法
塩を使った基本的な臭み取り
塩は、砂ずりの臭み取りにおいて最も手軽で基本的な方法です。
塩の浸透圧を利用して、砂ずりの内部にある余分な水分や、臭みの原因となるヌメリや血などを外に引き出す効果があります。
具体的な手順は以下の通りです。
- 銀皮の処理や切り分けなど、基本的な下処理を終えた砂ずりをボウルに入れます。
- 砂ずり全体に塩(適量、または重量の約1%程度)を振りかけます。
- 指でしっかりと揉み込みます(揉み洗い)。
- 揉み込むと、砂ずりから水分やヌメリが出てきて、塩が濁ってきます。これが臭みの元です。
- 数十秒〜1分ほど揉み込んだら、流水でしっかりと洗い流します。
- 砂ずりに残った塩分やヌメリを完全に洗い落としてください。
- 最後に、キッチンペーパーなどで水気を徹底的に拭き取ることが重要です。
ポイント:塩と酒の併用
塩で揉み洗いした後、水気を拭き取った砂ずりに、さらに少量の酒(小さじ1程度)を絡めてから再度水気を拭き取ると、より効果的に臭みを抑えることができます。
これは、塩で水分やヌメリを取り除き、酒で香りをマスキングするためです。
注意点として、揉み洗いした後の塩分やヌメリをしっかり洗い流さないと、塩辛くなったり、臭みが残ったりする原因になります。
酒を使った臭み取りの方法

酒(料理酒)も、砂ずりの臭み取りに非常に有効なアイテムです。
酒に含まれるアルコール成分には、臭みをマスキング(覆い隠す)する効果や、加熱時に臭み成分と一緒に揮発(蒸発)する働きがあります。
また、脂溶性の臭いを緩和するのにも役立ちます。
具体的な手順には、主に2つの方法があります。
方法1:揉み込む(塩と併用)
- 前述の通り、塩と酒(酒塩)を一緒に振りかけ、しっかりと揉み込みます。
- ヌメリや濁りが出たら、流水でしっかり洗い流します。
方法2:浸け込む(下味として)
- 銀皮処理や切り込みを入れた砂ずりの水気をしっかり拭き取ります。
- ボウルに砂ずりを入れ、酒(砂ずり200gに対し大さじ1程度)を絡めます。
- そのまま5分〜10分程度冷蔵庫で置きます。
- 調理前に、キッチンペーパーで表面の余分な酒(水分)を拭き取ります。
酒を使うメリット
酒で下処理(特に方法2)を行うと、臭み取りだけでなく、肉質を柔らかく保つ効果も期待できます。
また、炒め物などにする際に、酒の風味が加わるメリットもあります。
使い分けとして、しっかり臭みの元(ヌメリなど)から落としたい場合は「方法1:揉み込む」、調理前の下味と香り付けを兼ねたい場合は「方法2:浸け込む」が適しています。
牛乳に浸ける臭み取りの効果

牛乳に浸ける方法は、特に内臓肉の臭み取りとして知られており、砂ずりにも応用できます。
理由として、牛乳に含まれるタンパク質「カゼイン」が、臭みの原因となる成分を吸着して取り除く働きがあるとされています。
具体的な手順は以下の通りです。
- 銀皮処理や切り込みを入れた砂ずりをバットやボウルに入れます。
- 砂ずりが浸る程度の牛乳を注ぎます。
- ラップをして、冷蔵庫で10分〜20分程度置きます。
- 時間が経ったら砂ずりを取り出し、流水で牛乳をきれいに洗い流します。
- 最後に、キッチンペーパーで水気を徹底的に拭き取ります。
牛乳を使う際の注意点
この方法は臭み取りの効果が高い一方で、いくつかの注意点があります。
- 洗い流しを徹底する: 牛乳が残っていると、加熱時に焦げ付いたり、風味が残ったりする原因になります。
- 風味がマイルドになる: 牛乳の風味がわずかに移ることがあり、仕上がりがまろやかになります。
これがメリットになる料理(唐揚げや煮込みなど)もありますが、シンプルな塩焼きなどでは好みが分かれる場合があります。 - 食感への影響: 砂ずり特有の強いコリコリ感が、ややマイルドになる(柔らかくなる)傾向があります。
使い分けとして、砂ずりの臭いが特に強いと感じる場合や、唐揚げ、煮込み料理など、まろやかな風味に仕上げたい場合に試してみる価値がある方法です。
砂肝を茹でる時間は何分が目安?

砂肝(砂ずり)を茹でる時間は、砂肝の状態(まるごとか、切ってあるか)と目的によって異なります。
茹で過ぎは身を硬くする原因となり、茹で時間が短すぎると中心まで火が通らず、臭みも残ってしまいます。
具体的な茹で時間の目安は以下の通りです。
方法1:下処理(銀皮取り)を省略する茹で方
- 状態: まるごと(銀皮付き)
- 目的: 臭み取りと、銀皮を柔らかくするため。
- 時間: 沸騰したお湯で 約12分〜15分
- (補足)この方法は、前述の「簡単な下処理方法」に該当します。茹でた後に水でよく洗います。
方法2:下茹で(調理の前処理)
- 状態: 銀皮を取り除き、半分や薄切りにカットした後
- 目的: 和え物や冷菜にするため。または火通りを均一にするため。
- 時間: 沸騰したお湯で 約3分〜5分
- (補足)中心部がうっすらピンク色から白っぽく変わったらすぐに引き上げ、余熱で火を通すのが硬くしないコツです。
方法3:和え物などで使う茹で方(ネギや生姜と)
- 状態: まるごと(銀皮付き、または取ったもの)
- 目的: 臭み消し(ネギの青い部分や生姜)と一緒に茹で、和え物などに使う。
- 時間: 沸騰したら火を弱め 約5分〜7分
- (補足)茹で上がったらザルにあげ、アクを洗い流してから薄切りにします。
美味しく茹でるコツ:温度
砂肝を柔らかく茹で上げたい場合、グラグラと沸騰させ続けるよりも、沸騰直前の温度(約80〜90℃)で穏やかに火を通す(低温で茹でる)と、タンパク質が急激に収縮せず、しっとりとした食感に仕上がりやすくなります。
茹でた後は氷水に落とすと、食感が引き締まります。
下処理後の砂ずりの保存方法

下処理を終えた砂ずり(砂肝)は傷みやすいため、冷蔵保存または冷凍保存で適切に管理する必要があります。
特に生の砂ずりは内臓肉であり、水分も多いため、常温放置は絶対に避けてください。
具体的な保存方法は以下の通りです。
冷蔵保存
すぐに(当日または翌日)使う場合の保存方法です。
- 生のまま(下処理済み):
- 塩揉みや酒などで臭み取りをした後、水気を完全に拭き取ります。
- 空気に触れないよう、ラップでぴったりと包みます。
- ジッパー付き保存袋などに入れ、空気を抜いて密閉し、冷蔵庫のチルド室など温度が低い場所で保存します。
- 保存目安: 約1日。
- 茹でた後(下処理済み):
- 茹でた砂ずりの水気をしっかり拭き取り、完全に冷まします。
- 生のままの場合と同様に、ラップで包み、保存袋に入れて密閉します。
- 保存目安: 約2〜3日。
冷凍保存
すぐに使わない場合は、冷凍保存がおすすめです。
- 生のまま(下処理済み):
- 水気を徹底的に拭き取ります。(水気は冷凍焼けや臭みの原因になります)
- 1回に使う分量ずつ小分けにし、ラップでぴったりと包みます。
- 冷凍用のジッパー付き保存袋に入れ、できるだけ平らにして空気を抜きます。
- 金属製のトレーなどに乗せて急速冷凍します。
- 保存目安: 約1〜2週間。(長くても1ヶ月以内には使い切りましょう)
- 茹でた後(下処理済み):
- 茹でた砂ずりをしっかり冷まし、水気を拭き取ります。
- 薄切りなど、使いやすい形にカットしてから小分けにすると便利です。
- 同様にラップで包み、保存袋に入れて急速冷凍します。
- 保存目安: 約1ヶ月。
冷凍砂ずりの解凍方法
冷凍した砂ずりを解凍する際は、冷蔵庫でゆっくり解凍するのが最もドリップ(旨味の流出)が少なく、おすすめです。
流水解凍や電子レンジの解凍機能も使えますが、加熱ムラやドリップが出やすくなるため注意が必要です。
砂ずりの下処理と臭み取りを総括
砂ずり(砂肝)の下処理と臭み取りは、少しの手間で料理の仕上がりを格段に良くする重要な工程です。
これまでのポイントを押さえることで、砂ずり特有の「硬さ」や「臭み」といった悩みを解消し、美味しい部分だけを最大限に楽しむことができます。
この記事のポイントをまとめます。
- 砂ずりと砂肝は同じ部位(鶏の砂嚢)
- 呼び方の違いは主に東日本(砂肝)と西日本(砂ずり)
- 砂嚢は胃の一部で筋肉が発達しコリコリした食感が特徴
- 下処理しないと銀皮が硬く臭みが残ることがある
- 強い刺激臭やぬめりは腐ってるサイン
- 簡単な下処理は銀皮を取らずに12分ほど丸ごと茹でる方法
- 茹でた後は水でよく洗い汚れや脂を落とす
- 本格的な下処理は青白い銀皮を包丁で削ぎ取る
- 銀皮はまな板に押し付け包丁を寝かせて引くと取りやすい
- 切り込み(川の字や格子状)で火通りと味染みを良くする
- 基本的な臭み取りは塩で揉み洗いし水で流す
- 酒は臭みのマスキングと揮発に役立つ
- 牛乳はカゼインが臭いを吸着するが風味はマイルドになる
- 茹で時間は目的(下処理か下茹deか)で変わる(3分〜15分)
- 下処理後の生の状態での冷蔵保存は1日が目安
- 下処理後の冷凍保存は2週間から1ヶ月が目安


